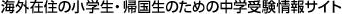工学院大学附属中学校・高等学校


工学院大学附属中学校・高等学校(以下工学院)は、八王子駅を初め、5つの駅からキャンパスまでスクールバスの運行がある極めて交通アクセスのよい学校です。特に新宿駅からの直行バスは約40分で学校に連れてきてもらえる(しかも無料!)ということで、都心に住む人にとっても利便性の高い学校なのです。
(取材・文/スタディエクステンション代表・鈴木裕之)
 工学院大学の附属校だけあって、理系に進学したいという希望を持つ生徒にとって魅力的なカリキュラムが組まれているのはもちろん、時代を先取りするグローバル教育を実践しています。2015年にハイブリッドインターコースを開設し、以来21世紀型教育を強力に推進してきました。その間に改革してきた内容を列挙するなら、ケンブリッジイングリッシュスクールへの加盟、CLIL(内容と言語の統合アプローチ)の推進、英語哲学授業およびSTEAM(理系とアートの総合的教育)の導入、世界貢献を実践するGlobal Project、そして世界中のエスタブリッシュな私立学校と連携する「ラウンドスクエア」への加盟など、枚挙に暇がありません。
工学院大学の附属校だけあって、理系に進学したいという希望を持つ生徒にとって魅力的なカリキュラムが組まれているのはもちろん、時代を先取りするグローバル教育を実践しています。2015年にハイブリッドインターコースを開設し、以来21世紀型教育を強力に推進してきました。その間に改革してきた内容を列挙するなら、ケンブリッジイングリッシュスクールへの加盟、CLIL(内容と言語の統合アプローチ)の推進、英語哲学授業およびSTEAM(理系とアートの総合的教育)の導入、世界貢献を実践するGlobal Project、そして世界中のエスタブリッシュな私立学校と連携する「ラウンドスクエア」への加盟など、枚挙に暇がありません。
いずれの改革も平方邦行先生が校長就任後に強力なリーダーシップを発揮し、教育研修や対話を重ねながら推進してきたものです。
「Growth Mindset」を育てる帰国生指導
このような学校改革は、他の私立学校にも波及しており、工学院は、帰国生教育の新たな潮流を牽引している学校だと言えます。かつて帰国生教育といえば、日本型の補習を行ったり、英語力を「保持する」ための英会話教室が行われたりするのが主流でした。こういった帰国生教育の考え方は、日本のスタンダードを身につける上で足りないところを補填しながら、アドバンテージを失わないようにするというものです。
しかし、工学院での帰国生教育のスタンダードは「グローバル」です。帰国生であれ、国内で学んできた生徒であれ、これからの社会では「世界」を基準にして自分の強みを発揮することが必要になってきます。そのようなことから工学院では、「帰国生は日本語が弱い」などといったステレオタイプな考え方はしません。日本人として必要となる日本語は当然身につけるけれども、画一的な基準の中で評価するのではなく、生徒の個性や学習特性などを考慮して、自分自身がどれだけ成長できたかという「Growth Mindset」を育成しているのです。
「世界」を視野に入れた進路指導
学校改革の成果の表れとして注目すべきは合格実績です。もともと工学系・理系の大学進学に定評のある工学院ですが、そこにグローバル教育の軸が加わったことで、国内大学の合格実績がさらに伸びています。実際、2019年度には東京工業大学や東京医科歯科大学、電気通信大学などの難関国立大学に15名、早慶上理に30名の合格者を輩出しました。改革に本格的に着手する前の卒業生ですが、学校の中に改革の「勢い」があるということでしょう。
また、海外大学に進学しようとする生徒にサポートを手厚く行っていることも見落とせません。2020年卒業予定の生徒はすでに、イギリスやアメリカなどの大学4校に合格しており、そのうちの3校は、THE(タイムズハイヤーエデュケーション)の世界大学ランキング200位以内の大学です。ちなみに日本の大学で200位以内に入っているのは東京大学と京都大学のみですから、工学院の海外大学合格実績がいかに凄いことかが分かります。
このように国内・海外を問わず生徒の強みを支える進路指導というのは、先生の方に不断の努力・研鑽が欠かせないですし、何より生徒とのコミュニケーションが充実していることの証です。
学びのシフトを可能にする「思考コード」
工学院が学校改革を急ピッチで進めたのは、この先に起こる社会変化と大きく関わっています。1990年の日本には2300万人以上いた15歳未満人口は今や1530万人まで減少しました。また、1989年には時価総額ランキングは日本企業が上位50位の中に33社が入っていましたが、現在はわずか1社です。
現在の小中学生が働き盛りになっている20年後は、世界の中で日本が占める存在感は人口的にも経済的にも相対的に低下せざるを得ないと予想されています。そのような状況下で未来をプラスに転換するためには、一人一人がそれぞれの才能や創造性を伸ばし続けることが必須となるわけで、教育に携わる人間はこういった状況を直視して世界の変化に対応するべきだと平方校長先生は強く訴えます。
そのために工学院では「思考コード」を活用して「思考の深さ」と「知識の広がり」を可視化しました。学びの次元をシフトする必要があるからです。この思考コードによって、単に知識をため込むような勉強から解放されて、生徒が自ら探究を進めていく学びへのシフトが可能になるのです。
グローバル・イマージョン
英語教育についても「英語を学ぶ」から「英語で何をするか」の次元へと学びのシフトが起こっています。
CLIL(内容と言語の統合アプローチ)をいち早く取り入れたのは、そういう考えの表れです。工学院の授業では、英語は単に考えを伝える「ツール」ではありません。思考と言語を切り離して考えないこと、つまり言語の学習は思考そのものを育成することだというスタンスで英語教育を実践しています。
 ハイブリッドインタークラスの英語の授業を覗かせていただくと、中学生が本格的なディベートを英語で行っていました。指導する先生は、英語のネイティブスピーカーで、生徒同士の打ち合わせもディベートそのものも英語で行われています。
ハイブリッドインタークラスの英語の授業を覗かせていただくと、中学生が本格的なディベートを英語で行っていました。指導する先生は、英語のネイティブスピーカーで、生徒同士の打ち合わせもディベートそのものも英語で行われています。
また別の教室では音楽のプロモーションビデオを観賞した後に、その映像分析を英語で進めていました。ミニプレゼンテーションや生徒同士の質疑応答も英語で行われます。
高次思考の英語力というのは、従来の日本型英語学習では、文法や訳読が一通り網羅された後に、できる人だけがやればよいと放置されてきた領域です。しかし、工学院は、まったく逆の考え方でアプローチします。高次思考を必要とする場面を提示することで、その場面に必要となる英語力が自然に習得されるという考え方、それこそが「グローバル・イマージョン」の考え方です。
さらに、こういったPBL(プロジェクト・ベースト・ラーニング=課題を設定しチームでその課題を解決していく授業)は、単に一部の教員が行うということではなく、学校全体で促進していく「仕組み」もあります。それは、外部機関の調査によるアクレディテーション(21世紀型教育の質認定)です。アクレディテーションを通して、学校全体に21世紀型教育が行き渡っているかどうかを検証しているのです。
哲学授業と対話と探究
新宿キャンパスを訪れた時にはJames先生が高校生20名ほどと一緒に英語で哲学授業を行っているところでした。
 ホワイトボードにはサンドイッチの断面の写真が10枚ほど掲示してあり、その写真を見ながら生徒と先生、あるいは生徒同士が対話しています。「哲学授業」と聞くと難しい用語を駆使して抽象的なことを議論していると想像する人もいるかもしれませんが、James先生が行う哲学授業は非常にシンプルです。しかし、そのシンプルな対話から始めて、深い意味に到達する機会を与えるところに哲学授業の魅力があるのです。
ホワイトボードにはサンドイッチの断面の写真が10枚ほど掲示してあり、その写真を見ながら生徒と先生、あるいは生徒同士が対話しています。「哲学授業」と聞くと難しい用語を駆使して抽象的なことを議論していると想像する人もいるかもしれませんが、James先生が行う哲学授業は非常にシンプルです。しかし、そのシンプルな対話から始めて、深い意味に到達する機会を与えるところに哲学授業の魅力があるのです。
 例えば、どのサンドイッチがおいしそうに見えるか、そしてそれはなぜかという一見雑談風の話をしながら、私たちがおいしそうだと感じるのは食べた経験から判断しているのか、それとも色合いなどから推測しているのかといった問いかけが起こります。このような問いかけが哲学授業の入り口です。生徒たちぐるりと円を作って座っているのですが、その隣同士の2人で考えを述べ合うように促されます。それから、その対話から出てきた意見を全体に向かって発表し合います。他の生徒が話している間はしっかり聞くというルールがあり、挙手で指名された生徒が発言する時間です。
例えば、どのサンドイッチがおいしそうに見えるか、そしてそれはなぜかという一見雑談風の話をしながら、私たちがおいしそうだと感じるのは食べた経験から判断しているのか、それとも色合いなどから推測しているのかといった問いかけが起こります。このような問いかけが哲学授業の入り口です。生徒たちぐるりと円を作って座っているのですが、その隣同士の2人で考えを述べ合うように促されます。それから、その対話から出てきた意見を全体に向かって発表し合います。他の生徒が話している間はしっかり聞くというルールがあり、挙手で指名された生徒が発言する時間です。
ジェームズ先生はあるときは生徒同士の対話をうながし、またある時には発言者の考えに対する賛成意見や反対意見を求めながら、対話の方向を舵取りしていくのです(こういった哲学授業のノウハウや理論的背景についてはジェームズ先生の著書『Thinking Experiments』に詳しく書かれています)。
このような対話授業では、生徒の積極的な「参加」が必須条件です。工学院で哲学授業がうまく進んでいるのは、もともと海外で同様の授業を受けていた帰国生が多いことはもちろんですが、探究論文という活動や、先に紹介したPILやPBLの授業が学校全体に広がっていることが大きく関係しています。自分で問いを立てて考えを進めることが奨励され、生徒たちもそれを習慣化しているのです。そのような生徒の存在があることによって哲学授業も成立・発展していくわけです。
イノベーションを引き起こすSTEAM教育
STEMとは、サイエンス・テクノロジー・エンジニアリング・マスマティクス(数学)の頭文字を取ったもので、オバマ前大統領が米国の工学系人材不足の打開策としてSTEM教育予算を増やしたことで知られるようになりました。
そのSTEM教育にアートを加えたのがSTEAM教育です。工学的な教育は大切ですが、ただのモノづくりで終わるのではなく、デザイン思考や哲学的思考を取り入れ、イノベーションを引き起こす力を養うことが工学院のSTEAM教育の目的です。
そのSTEAM教育のハブとして機能するのがFabラボです。工学院では、図書館の中に工学プログラムなどが体験できるスペースを確保し、そこで生徒が3DプリンターやVR機器などを自由に利用できるようにしています。
また、中学校ではデザイン思考の授業を週に1時間採り入れ、アイディアを形にしていくプロセスを学んでいきます。
このように、工学とアートが融合する学びを推進する工学院の源流は、工学院大学の創立に関わった建築家にまで遡ることができます。工学院の改革は伝統の上に進められているわけです。