学校特集
実践学園中学・高等学校2025
新教頭が語る、教育への想い
掲載日:2025年10月22日(水)
2027年に建学100周年を迎える実践学園中学・高等学校。教育理念「豊かな人間味のある、真のグローバル人材の育成」のもと、リベラルアーツ&サイエンス教育、海外研修・留学など多彩なプログラムを積極的に取り入れながら、時代の変化に合わせて進化を続けてきました。今回お話を伺ったのは、2025年度から中学校教頭を務める國澤朋美先生。同校の中高一貫部の取り組みや教育、そして学校運営への抱負を語っていただきました。
豊富なキャリアを活かした
"対話力"で生徒と向き合う

教頭の國澤朋美先生が実践学園に教員として赴任したのは2017年のこと。それ以前は、私立女子校教員や公立小中学校で講師を務めたのち、専業主婦として3人の子育てを経験。子育ての傍ら、地域に根差した体操・ダンス教室を立ち上げ、会社を起業するなど多様な経験を重ねてきました。
「主人と子どもたちが後押ししてくれ、再び学校に戻ることを決意しました。その際、ご縁があったのが実践学園でした」(國澤先生)
着任当初は養護教諭として採用された國澤先生でしたが、ダンスや体育の指導経験が評価され、保健室と体育の教員を兼務するように。そのうちに保健室の仕事からは外れ、中学校で担任を持ったり、中高女子ダンス部の顧問を務めたりするようになったと話します。
そして、2025年度から同校の教頭に就任しました。國澤先生自身は、まったくの想定外で打診された際にはとても驚いたそうですが、「生徒指導の経験や、子育ての経験をぜひ活かしてほしい」という周囲の言葉もあり受諾したと話します。日頃、生徒たちと触れ合うなかで大事にしてきたことを尋ねると、こんな答えが返ってきました。
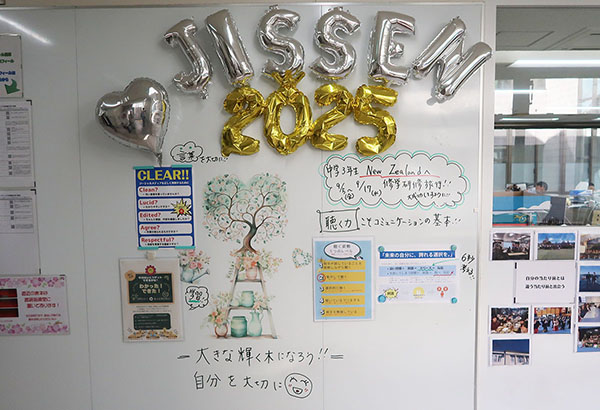
「多感な年頃ですし、生徒が納得しないまま一方的にこちらの考えや意見を押し付けることはしたくないので、納得するまでとことん話すこと、生徒の考えを聞くことを大切にしています。ときに"世の中では、認められないこともあるんだよ"と、説明することもあります。そして、指導した子と廊下ですれ違った際などには"その後、どう?"と声をかけるようにしています。以前、スカートの長さやお化粧について何度も注意していた生徒がいたのですが、高校卒業後まもなくして"先生と話したい"と来校してくれて、"(あのときは)自分が間違っていた"と話してくれました。きっと、我々教員が生徒に注意していることの多くは、そのうち生徒自身がいつか自分で気づくこと。だからといって見過ごしていいわけではなく、きちんと指導できる教師でいたいと思っています」
國澤先生が話す卒業生のエピソードは、厳しさと温かさを兼ね備えた指導が、生徒の心に印象深く残った証でしょう。対話やコミュニケーションの大切さは、自身の子育てや幅広い世代にダンスを教えた経験などから得た気づきでもあり、現在の教育現場でも活かせていると國澤先生は自負しています。子育てを通してたくさんの人とつながり、自身が成長させてもらったという実感があるため、保護者会では『子育てはあっという間です。楽しんでくださいね』と伝えていると言います。
能動的に取り組む生徒が増加中!
今後は英語力の向上を目指す
実践学園では生徒同士が協働し、挑戦する機会を多く設けています。その効果もあり、以前は活発な生徒とおとなしい生徒の二極化が見られたそうですが、現在ではその傾向は緩和され、前向きにさまざまなことに取り組む生徒が増えました。そのきっかけとなる機会づくりについて、國澤先生はこう説明します。

「例えば昨年度は、中学1年生が総合学習でパスタ、テープ、ひも、マシュマロを使って自立可能なタワーを立てる『マシュマロチャレンジ』というチームビルディングのための活動を行いました。クラスを横断してチームをつくったため、普段はあまり関わりのない生徒同士が協力し合う、仲良くなるきっかけになりました。そして秋の文化祭では、その経験を生かして中学1年生の催しとして『マシュマロチャレンジ』コーナーを実施。来校者に向けて、ルールを説明する子、運営をサポートする子など、それぞれがシフトを組んで役割を担って行いました。これらの取り組みを通じ、生徒たちはそれぞれ対等に意見を出し合う・足並みを揃えながら活動するようになったと思いますし、団結力や達成感を感じられるようになったと思います。教員側は、少しでもいいからやり切ったという達成感や、やって面白かったと感じてほしいという願いでさまざまな機会づくりに励んでいます」
同校で特徴的なのは、生徒だけでなく教員同士のチームワークも重視している点です。教員研修では、コミュニケーションデザインの授業を担当する森 圭司先生の提案で、レゴ®ブロックを使い「理想のホームルーム」を表現するなど、遊び心を交えつつ教育理念を共有しています。
「学年ごとに先生方がよく相談し合い、生徒情報を共有している姿を見て、とても心強く感じています。教員同士の連携を深め、生徒を育てていくという熱意が、学校全体に根付いていると感じます」(國澤先生)
そして教頭として新たな役割を担ういま、國澤先生は「学ぶ楽しさを軸とした学力向上」も見据えています。

「実践学園中学の大きな目玉行事のひとつが、中3で実施するニュージーランド修学研修旅行です。この貴重な機会を生かし、帰国後には全員が英検準2級を取得できるような学習姿勢を築いていけたらと考えています。そのためには日々の授業を大切にし、達成感を得られる学びを積み重ねていくことが大事です。そうした授業展開を各授業担当の先生方に依頼しています。生徒たちには自分で学びを深めていく楽しさを味わってほしいと願います。そして学校が見守っているということを生徒たちが感じ、安心して勉強に励めるようにサポートしていきます。困った時にはどんどん頼れる、そんな学校にしたいと考えています」
その言葉を裏付けるように、國澤先生は教頭に着任して以降、授業巡回を頻繁に行い、ときには教室に入って様子を見守っているそうです。國澤先生のそうした姿は、きっと生徒たちや教員たちに安心感を与えていることでしょう。
伝統校でありながら、
教育革新を続けてきた先進校
2年後には創立100周年を迎える実践学園。歴史と伝統がありながらも、先進的な教育に果敢に取り組んできました。なかでも①グローバル教育、②リベラルアーツ&サイエンス教育、③手厚い進学指導(J・スクール)は、同校の大きな特色です。それぞれについて、國澤先生は以下のように説明します。

① グローバル教育について
「本校のグローバル教育は、語学の習得を目的とするだけではなく、グローバル社会で通用する幅広い見識と確固たる信念を持った人間の育成を目指しています。そのため、中高6カ年を通し、多彩な海外留学・語学研修プログラムや、グローバルな視点からの教育を実施。なかでも中3時の必修行事である2週間のニュージーランド修学研修旅行は、生徒の価値観を大きく変えたり、今後の学びを促進したりするような有意義な体験です。特に、発信力、自己表現力を飛躍的にアップさせてくれます」
同校の生徒は、基本的に現地の1家庭にひとりでホームステイさせていただき2週間を過ごします。帰国後はひとつ下の後輩たちに向けて現地での様子や学んだことをプレゼンします。高校では、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、アメリカなどの短期・長期プログラムが用意されているので、希望制で参加することも可能です。実際、中3時のニュージーランド修学研修旅行をきっかけに英語や海外への興味・関心を高め、高校で再度海外研修や留学に行く生徒も多いのだそうです。

② リベラルアーツ&サイエンス教育について
「本校では『リベラルアーツ&サイエンスクラス』を中2から希望できます。このクラスが大きな目的として掲げているのは、グローバルリーダーの育成です。ネイティブ教員が副担任として就くため、英語力は大きく向上します。
高1時にカナダの語学研修があるため、中3時のニュージーランドと合わせて2回留学に行くことになります。
また、毎年12月には中高のリベラルアーツ&サイエンスクラスの生徒を対象とした『実践ライブ』が行われ、生徒は社会課題の解決アプローチについて英語で発表を行います」
同校では、「リベラルアーツ&サイエンスクラス」以外にも、学校全体でリベラルアーツ&サイエンス教育に力を注いでいます。例えば、中学校では学校内にある「実践の森・農園」を活用した自然環境教育を行うほか、高校では著名な大学教授を招いて大学模擬授業を実施。また2023年からSTEAM教育も開始し、生徒たちはロボットプログラミングなどにチャレンジしています。
③ 手厚い進学指導(J・スクール)について
「中学では、『ジュニアJ・スクール』、高校では『J・スクール』を実施しています。『ジュニアJ・スクール』は、主に放課後や長期休みに行われているもので、英語と数学を中心に基礎をしっかりと固めながら、応用力を培う内容です。今後に向けた学習習慣づくりも兼ねています。
一方の『J・スクール』は、経験豊富な予備校講師と本校の教員によって行われます。講座内容とテキストの作成は、予備校講師と学園の教科担当教員が綿密な打ち合わせを行って決定し、そのカリキュラムは普段の授業と一体化したものです。日常の授業で学んだ知識を『J・スクール』講座で確認し応用することで、大学入試に必要な基礎学力の定着と応用力の育成を図る『深堀学習→発展演習』を実現しています。本校の生徒に最適なカリキュラムとオリジナルテキストにより、多くの生徒が志望大学に合格しています」

「J・スクール」は、一般的な塾や予備校と比べるとあらゆる面で負担が少ないため、生徒の学ぶ意欲を大きく後押ししてくれる心強い味方です。難関大学への進学実績も年々伸びており、2025年度は国公立大へ計8名、早慶上理へ計17名、MARCHGへ計94名が進学しています。
最後に、國澤先生は自身の高校時代を振り返りながら、抱負を語ってくれました。
「高校生のときに始めた創作ダンスは、現在の自分の礎となっています。当時の先生とはいまも交流が続いていますし、創作ダンスを通じたさまざまな出会いや経験に対して感謝の気持ちでいっぱいです。本校の生徒たちにも、そんな風に思える学校生活を送れるように最大限サポートしたいと強く思います。

中学・高校時代は『人としてよりよく豊かに生きる』力を身につける、とても大切な発達時期です。人間の脳の発達は3歳ぐらいまでに80パーセントが完成し、残りの20パーセントは、中学・高校の時期に発達して完成されると言われています。この20パーセントの発達部分というのは、相手を思いやる気持ちをもつことや、『ここぞ』という時に頑張れる力だと思います。様々な体験ができる場、感動できる場、他者と協働できる場を学校がどんどん提供し、子どもたちの心の豊かさを育み、成長をサポートしてあげたいです」
「人としてよりよく豊かに生きる力」――それは、大学進学後、そして社会に出てからも必ず必要な力です。実り多き中学・高校時代を過ごし、将来は自分の抱く夢を実現させたいと考える受験生にとって、まさにふさわしい学校といえるでしょう。





