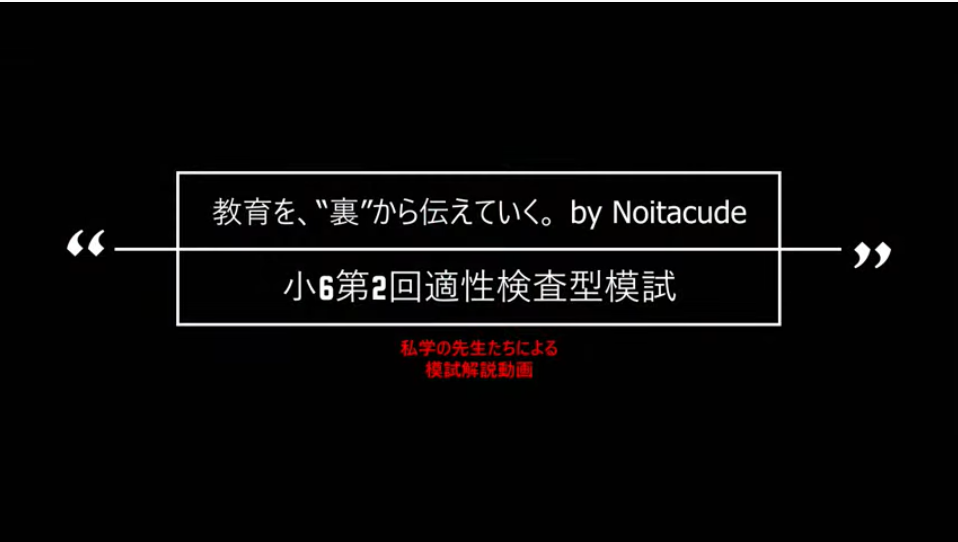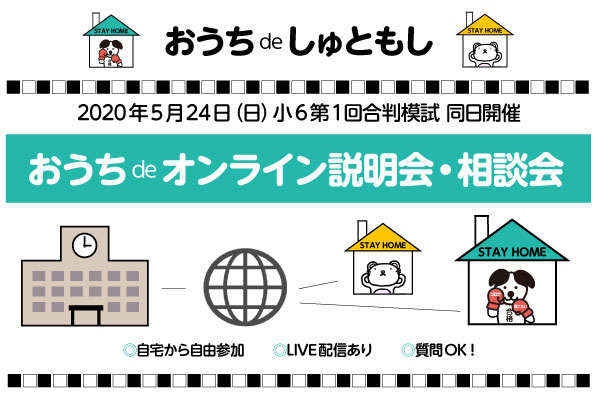LOVELY LIBRARY 第23回·品川翔英中高の図書館《特別編》
情報誌『shuTOMO』2025年9月15日号でご紹介した品川翔英中学校高等学校の「LOVELY LIBRARY」取材時に先生方に伺ったお話を、特別編としてWebでお伝えします。〈取材・撮影・文/ブランニュー・金子裕美〉
職員室の座席はフリーアドレス

-図書室は新しい教育を行う象徴的な場所になりつつありますが、新校舎を建てる際に、他にも工夫した点があれば教えてください。
本川先生 現在の校舎には、教室と廊下を隔てる壁がありません。いろいろな形で授業ができるように、オープンスペースにしています。食事をしたり、面談をしたり、勉強をしたりする場所としてカフェテリアもできました。そういう場所ができても、使いこなさなければ意味がないので、教員同士がコミュニケーションをとり、新しい発想を生み出す一つの手段として、職員室の座席を決めていません。フリーアドレスなんです。毎朝抽選して、どこに座るかを決めています。メンター制度も導入しています。生徒が困った時に、担任の先生だけでなく、誰に相談してもいいということになっています。

ー物質的な壁だけでなく、心の壁もとっぱらう工夫をしているのですね。
本川先生 在校生だけでなく、学校説明会に足を運んでくれた受験生の反応が変わって、いいなと思ってくれるとすごく嬉しいんですよね。
剣持さん 入学後に図書室に来て「図書室を見て、ここに決めました」という話をしてくれる生徒もいます。私たちも、その言葉に力をもらっています。
本川先生 司書の皆さんがオープンキャンパスや志ら梅祭(文化祭)にも企画を出してくれるので大変ありがたいです。
人工芝の上で青空図書室を開室したい

ーこれからやってみたいことはありますか。
前畑さん 映画上映会をやりたいという話はしていますよね。原作のある映画を、いつかここ(図書室)でやってみたいと思っているんです。それから、せっかく人工芝なので、そこにたくさん本を持って行って青空図書室をやりたいです。5月とか気候のいい時に、みんなで本を読みながらリラックスできる、そういう場所を作りたいです。
剣持さん 素敵な発想ですよね。私は学外の中高生と交流する場を増やせたらいいなと思っています。委員会活動がないので、「もうこんな本を読んでるんだ」というような刺激を受けることも必要かなと思うので、品川区内の学校図書館研究会で話をしてみようかなと思っています。
高田さん ビブリオバトルもそういう機会になっていますよね。去年、区の大会に参加させてもらった生徒がいました。図書室は閉鎖的な場所の代表みたいなところがあるので、図書室をきっかけに外に飛び出していくということも、体現できるようにしていきたいと思っています。それで今、私が先頭を切ってやらせてもらっているのが、企業や公共図書館とのコラボレーションです。昨年度は品川区の大井図書館、紀伊國屋書店さん。有隣堂さんとコラボさせていただきました。基本的には、選書していただいた本を、この図書室の棚に置かせていただくのですが、ポップまで作ってくださったり、人気のYouTubeを流す許可をくださったり……と、思わぬご協力をいただいて感謝しています。
学外の人が選ぶ本の棚を作りたい

-企業や公共図書館とのコラボには、どのようなメリットを感じていますか。
高田さん この企画は、学外で働いている方に本を選んでもらうことに意味があると思っています。我々3人の脳で考えることには限りがあるので、いろいろな経験値をもつ方が選書してくださった本を読むことによって生徒の興味関心は広がるはずですし、面白さを感じてもらえるはずだと思って始めました。場所柄、学校の近くにさまざまな企業がたくさんあるので、これからもアプローチして、いずれ専用の棚を設けることができたらいいなと思っています。
剣持さん コラボをきっかけに、図書館や書店に「行ったよ」という生徒もいます。
-効果てき面ですね!
高田さん 今度、有隣堂さんに、本校の生徒が選書した本を置いていただけることになったので、それもちょっと楽しみです。
剣持さん 「読書好きだけの場所にしないでほしい」「間口を広げてほしい」ということも、最初に言われたことの1つです。どうすれば本を取りやすい図書室にできるか、というところは、常に意識して運営しています。
-小学校の図書室との連携はいかがですか。
高田さん 今年度から私が兼任させてもらっています。小学校の図書室にも司書が1人いるので、いずれは小中高の図書室運営を一体化して、司書もどちらでも仕事ができるような形になればいいなと思っています。雨の日も濡れずに校舎を行き来できるので、1つの学園として蔵書を扱うことによって、例えば幼稚園で行っているお話会を、中高の図書室を使って実施することもできるでしょうから、横のつながりもしっかり構築していきたいと思っています。
読書会で現れた「読書ってなんだろう」という疑問

-本の選び方もそれぞれなんですか。
剣持さん 違いますよね。
高田さん 剣持はディープだよね。私はどうだろう。経済、社会に関する本や、ビジネス書、元々建築の仕事をしてたので、建築の本も選んでいます。
剣持さん 前畑は絵本やエッセイ、詩、あるいは家庭に根ざした本も選んでくれます。例えば、お弁当などごはん系の本は、4月に結構貸出があったので、関連本を集めて展示してみようかなと思っています。読書会をした時も面白かったですよ。
前畑さん みんなで同じ本を読むのですが、みんな、読み方が違うんです。剣持は灰色の空間に登場人物を置いて、高速でしゃべらせるということを頭でやりながら本を読むらしいです。
高田さん その時は小説を読んだのですが、剣持には風景がないんです。
剣持さん 本当にそうなんです。
高田さん 逆に僕は館などが出てくると、すべての間取りやデザイン、家具の配置などを考えながら読むので、ものすごく時間がかかります。
剣持さん (読み方が違い過ぎて)読書ってなんだろうと思いました。前畑は感情移入タイプです。
前畑さん そう。没入しちゃうので……。
剣持さん 私は構成にひっかかるんです。作家的な意図がこうだとか、アカデミックなとらえ方をしてしまいがちなので、読書では泣きません。
前畑さん たくさん本を読んでいるのに、「本を読んで泣いたことがない」と言うので驚きました。
剣持さん 私は頭が固いので、(周囲から)教えていただくことが多いです。「固すぎるよ」「真面目すぎるよ」って。
高田さん そこがいいんだけどね。
前畑さん 筋が通っているというのは、大事なことだと思います。
高田さん 僕らは同じスタートラインに立って図書室づくりを始めたので、「僕は思ってもいなかったけど、いいよね、それ」みたいなことを、ひたすらやってきた気がします。読書会は、そのうち生徒ともやりたいと思っています。それぞれの違いを認め合うきっかけになるんじゃないかなと思います。
品川翔英の図書室は、ぜひ一度、訪れていただきたい図書室です。常時1000冊ほどしか本を置いていません。書棚の下段にある本がほこりを被ることがないくらい、本を回転させることによって、豊かな蔵書をできるだけ面出しし、生徒が手を伸ばす機会を創るという独自の方法を見出し、実践しています。都会を見渡せる素晴らしい眺望、書棚の少なさ、三者三様の司書の皆さんが、新鮮な驚きと楽しさを味わわせてくれるに違いありません。
- この記事をシェアする