ミライ教育watching座談会【探究学習編】(25年5月実施)Vol.1
my TYPE第13号(2025年7月13日発行)掲載
主催・ファシリテーター:ミライクリエ
中学入試情報誌『MyTYPE』とは

『MyTYPE』は、首都圏模試センターが発行する中学入試情報誌で、最新の入試動向や学校情報をわかりやすく紹介しています。偏差値データや合格者分析に加え、受験生の「タイプ」に応じた学校選びの視点が特徴です。学力だけでなく個性や学び方に合った進路を考えるヒントが得られ、保護者にとっても教育方針や学校生活を知る貴重な情報源となります。受験を通じて子どもの未来を見つめるきっかけとなる一冊です。今回は、2025年7月13日発行のmy TYPE第13号に掲載しました記事をご紹介します。
▼my TYPE 購入はコチラ
・『しゅともしCLUB』
ミライ教育Watching座談会とは!?

私学の教育者・先生方をお招きし、「ミライ教育Watching座談会未来の教育を語る(探究学習編)」を開催しました。近年、教育のあり方は変化し、知識の暗記に加え、思考力・創造力・問題解決能力が求められる時代となっています。座談会には各私学の教育者・先生方が集まり、未来の学びについて活発な議論が交わされました。受験を控える受験生や保護者の皆様にとって、進路選択の参考となる貴重な機会となるでしょう。
(主催・ファシリテーター:ミライクリエ)
1)従来の学習と探究学習の違いについて
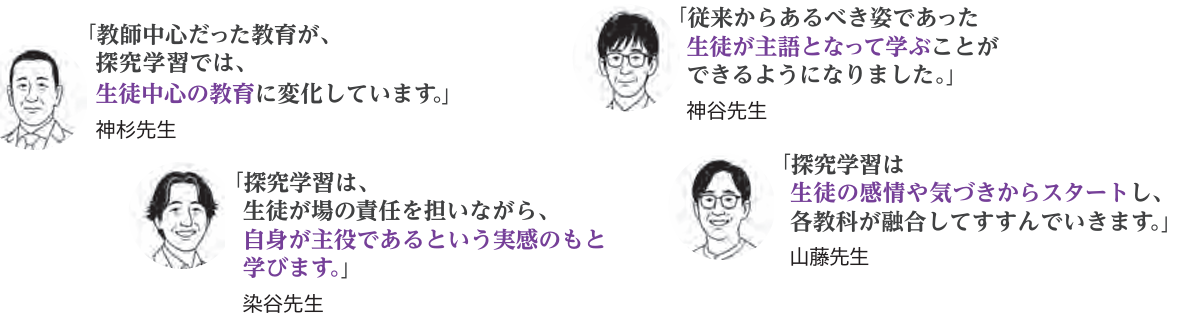
「従来の学習」と「探究学習」の違いとその背景について、教えていただけますか。
【神杉先生】:従来の学習は、教科の枠組みに沿って決められた内容を淡々とこなす形式でした。一方、探究学習では、生徒がいかに主体的に行動するかが重要なポイントになります。教師中心だった教育のスタンスが、生徒中心へと変化していると感じています。
【山藤先生】:神杉先生と同意見です。探究学習は、生徒の感情や気づきから始まるものであり、従来の学習は、学習指導要領と検定教科書を基にスタートするという点に違いがあると思います。もともと従来の学習にも探究学習の要素は含まれていたと思いますが、その割合が変化し、現在では探究学習の中に従来の学習が組み込まれるようになってきています。各教科を横断的に活用し、自分で立てた問いの解決に向かって学びを深めていくのが特徴です。探究学習では、各教科が融合していく感覚があります。
【神谷先生】:お二人がおっしゃったように、探究学習では、生徒が主体となることが重要なポイントだと思います。また、各教科を横断的に活用することは、本来あるべき学習の姿だったと考えます。生徒が主体的に取り組むことで、その学習方法がより整い、実践しやすくなったと感じています。
【染谷先生】:探究学習とは、生徒が学びの中心にいることを実感できる学習だと考えています。つまり、生徒自身が学びの責任を担っていると感じられる学習スタイルのことです。単に「生徒が主役」と前向きに伝えるだけではなく、実際に学びの責任を生徒自身が実感できる環境を整えることこそが、探究学習の真の価値であると考えています。探究学習にはさまざまな方法がありますが、学びの責任がどの程度生徒に委ねられているかという点に着目すると、それらの違いがよく見えてきます。この点を意識して各校の探究学習のスタイルを捉えることで、受験生の学校選びがスムーズに進むのではないかと考えています。
【山藤先生】:生徒のふとした疑問や感情が動いたところからスタートするのが探究学習です。その結果、本当に多種多様なテーマの活動が生まれてきます。与えられたテーマの中から選択するという枠組みがあり、その後は自分で進める場合もありますが、最終的には、1人1人の生徒が自分らしいテーマを決めていく状態が理想的だと思います。これが、先ほどおっしゃっていた「学びの責任」といえるでしょう。受験生の視点から見ると、それぞれの学校には多様な生徒による探究活動があり、それがどのように魅力的なのかを知ることが重要です。そして、自分に合いそうな活動を見つけ、選択していくことが大切だと考えます。

(写真:城西大学附属城西中学・高等学校 神杉 旨宣先生)
「探究学習」をすすめていくのにあたって、学校で意識されていることはありますか。
【神谷先生】:探究学習の問いは、自分だけで立てることが容易ではなく、他者との関わりが多ければ多いほど、より深く見つけていけるものだと考えます。従来の学習は学校内で完結していましたが、探究学習においては学校外での経験が不可欠であり、その機会を学校が積極的に提供することが非常に重要だと考えています。幼少期から問いを持っている生徒は少ないため、学校では外部の方を招いて特別講座を開催するなど、問いを育む機会を意図的に設けています。学校の先生だけでなく、さまざまな分野の大人との接点を増やすことが、生徒にとって新たな視点を得るきっかけとなり、探究の質を高めるうえで重要だと感じています。
2)探究学習のメリット、 未来・将来へのつながり
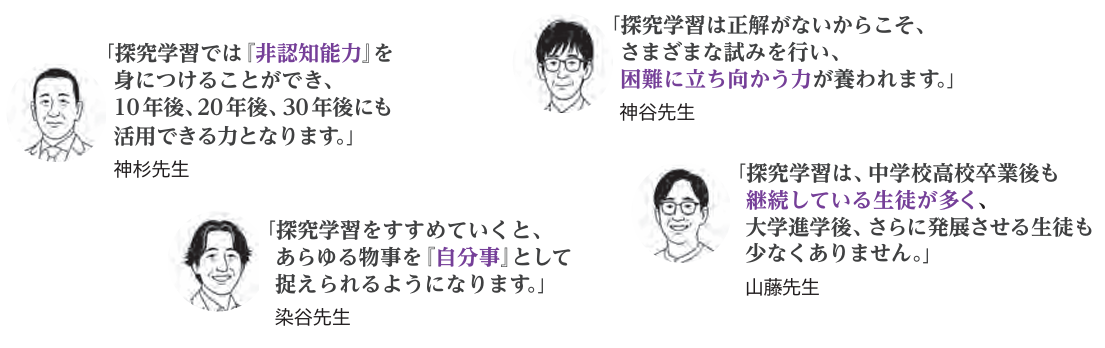
「探究学習」のメリットを教えてください。
【染谷先生】:探究学習を進めることで、生徒は学びの責任が自分自身にあることを実感します。その結果、あらゆる物事を「自分事」として捉えるようになる姿を、これまで多く目にしてきました。例えば、朝のニュース番組を見た際、多くの人は距離を置いて他人事のように受け止めがちです。しかし、探究学習を経験した生徒たちは、目の前の情報に自然と心を寄せ、何か心が動かされたときにはその感情を自覚し、「自分にできることはないか」などと考えられるようになっていきます。
【神谷先生】:探究学習は、正解がないという点が教科学習との違いです。正解がないからこそ、さまざまな試みを行い、失敗を経験することが当たり前になります。その過程で、困難に立ち向かう力が養われます。品川女子学院での事例をご紹介します。生理に関する問題意識を持って取り組んだチームは、男子の意識が変わらなければ状況は改善されないことに気づきました。そこで、男子校で出前授業を行うためにはどうすればよいか、交渉を含め試行錯誤を重ねました。このような経験を通じて、困難に直面してもくじけない強さが身につくと考えています。
【山藤先生】:探究学習は、中学校や高校という限られた時間の中で終わるものではなく、卒業後も継続している生徒が多いです。大学進学後、さらに発展させる生徒も少なくありません。学校での学習と社会がつながり、生徒は親や教師とは異なる立場の大人から承認される経験を得ます。それによって「自分が社会を少し良くできた」と実感できる生徒が増え、そのような経験を持った生徒が社会へと巣立っていくことは、未来にとって良い影響をもたらすと考えます。
【神杉先生】:探究学習では、知識や技術だけでなく、個々の人格や性格、価値観などを表す「非認知能力」を身につけることができます。それは10年後、20年後、30年後にも活用できる力となるでしょう。また、探究学習では、生徒が学校外の第三者から評価を受けます。自分が導き出した答えが正しいと感じたとき、自己肯定感が高まります。しかし、後に異なる答えにたどり着いたとき、以前の考えが誤っていたことに気づき、その気づきが苦しみを生むことがあります。このことが連鎖的に続くこともありますが、人生は一度きり。その中で最終的に自分なりの答えを見出すことが求められます。この過程こそが、未来への深い探究につながっていくのではないでしょうか。

(写真:文化学園大学杉並中学・高等学校 染谷 昌亮先生)
「探究学習」を進めることによって、未来や将来へどのようにつながるのかを教えてください。
【染谷先生】:文化学園大学杉並では、卒業生たちが授業や課外活動を手伝いたいと申し出てくれることがあります。学びの場を卒業しても、関わったコミュニティを自分事として捉え、後輩たちのために貢献しようとする姿勢が見られるのは非常に嬉しいことです。もちろん、卒業後は自由にのびのびと過ごしてほしいという気持ちもありますが、それと同時に、学校という学びの場への愛着やつながりが続いていくのはとても意義深いことだと考えています。
【神杉先生】:城西大学附属城西では、コロナを契機に、西日本では修学旅行の短期的な要素を取り入れた地域創生活動が行われています。その中で、限界集落でのプレゼンテーションを通じて、複数のグループのアイデアのうち一つが採用され、町おこしに貢献しました。この活動を経験した生徒たちは、総合型選抜を通じて大学に進学し、自らの経験を大学の仲間にも広めたいと考え、「探究」サークルを設立。現在、都立高校を巡って普及活動を行っています。
- この記事をシェアする


